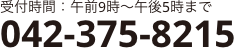ビザ取得から食材確保まで~ラーメン店の海外出店プロセス
調理師資格の取得を目指す人の多くは、将来的に「食」に関する仕事に就きたい・携わりたい、料理人になりたいなどを考えている傾向にありますが、近年では日本の食文化におけるインバウンド需要の高まりなどを背景に、「海外で自分の店を出すのが夢」というグローバルな視野を持った生徒さんも増えつつあります。
前回記事「▼夢は大きく海外出店!卒業から独立、海外出店までのサクセスストーリー」でもご紹介したように、今や日本の「日常的な食文化」ですら、
外国人にとっては魅力的なコンテンツに成長
していることを考えると、将来的な成功の可能性は海外の方が高いと考えるのが普通かもしれません。さらには、ラーメンや天ぷら、カツカレーなど、寿司のように長期間の修行が必要になる訳ではない身近な料理へのニーズが高まっていることを考慮すると
知識や資金さえあればすぐに繁盛店を作れそう
と考えてしまうのも致し方ないところではありますが、当然海外出店ともなると、単に提供する料理だけを考えれば良いわけではないことは言うまでもありません。上述いたしました前回記事では、海外への出店プロセスとして
・その土地の文化や商慣習を理解すること ・現地の人の味覚に合わせたレシピの開発 ・その国・その地域の法律や規制に対する理解
が重要だというお話をいたしましたが、今回の記事で取り上げるのが
各エリアごとに異なる法規制や許認可の違い
という点にフォーカスし、特に近年人気が高まっている「ラーメン店」を海外で開業するという仮定で、その出店までのプロセスを詳しく掘り下げて見ていきたいと思います。
海外でラーメン店の出店を目指す人の多くは「味には絶対の自信がある」といったことを口にしますが、現地の法規制や営業許可、税務・労務といった初歩的な手続きを軽視すると、いくら味に自信があっても海外出店は絶対に成功しません。専門学校卒業直後に資金が潤沢にあるということも珍しいかもしれませんが、
いくら腕があろうが資金があろうが法規制が立ちはだかる
ということを前提に、情熱や熱意だけでは解決できない部分をしっかりと押さえておくことが非常に重要となってきます。
まず、海外で働くためにはビザの取得が必須となりますが、そもそもビザが下りない可能性も十分にありますし、現地での店舗物件の問題、法人設立から事業登録、営業許可申請、衛生食品安全計画、人を雇う上での労務の問題など、もちろん国やエリアによっても違いはありますが、それらをすべてクリアして初めて営業が開始できるのです。
果たしてこうした実務を現実的に行うことができるのか?
その点も踏まえて、この記事では海外出店までの実務的なフローを詳しくご紹介していきたいと思います。舞台は海外となりますので、当然日本の常識は通用しませんし、「味には自信がある」だけでは
成功はおろか、出店すらできないというのが現実
それを肝に銘じたうえで、諸外国におけるラーメン屋の出店例を詳しく見ていきましょう。
■関連記事
どんなことを学ぶの?!技術から理論まで独立開業も見据えた授業内容あれこれ

調理の腕や資格だけでは論外?!国ごとに異なる法律・規制領域
海外出店を目指す人の多くは、マーケットの規模が大きいアメリカ本土やヨーロッパなどを検討する方が多いかもしれません。こちらの記事は、あくまで調理師資格を取得した専門学校卒業生が目指す場合のプロセスの概要説明に留まるため、あまり専門的で具体性の伴った内容ではありませんが、ラーメン屋出店に伴う大まかな必要手続きやプロセスをご紹介していきます。
1,現地法人の設立(LLCや株式会社など)
ラーメン屋と言えど、まず基本的に現地法人の設立が無難で、例えばアメリカの場合、各州政府や市の営業許可、そして渡航ビザも取りやすくなるようです。フランスやドイツといった欧州諸国も同様で、商業登記と併せて税務番号を取得する流れは概ねアメリカと一緒です。
アメリカの場合、週によってその法規や費用が異なるのですが、会社設立、営業許可申請、保健所許可申請、消防手続きなどで、概ね$2,000~$3,000前後が、初期コストとして必要となります。
2,渡航ビザの問題
もちろん、ビザが下りなければ現地で就労することもできませんので、最初にクリアしておかなければならない問題ではあり、これで躓いてしまうと、言うまでもなく海外出店どころの話ではなくなってしまいます。取得するビザについては、この記事で詳細に触れることはいたしませんが、
・アメリカ:E-2投資家ビザ ・フランス:起業家ビザ ・ドイツ →:自営業ビザ
を申請するのが一般的なようです。
ただし、海外での現地法人を設立しただけでは審査は通らないと言われており、会社設立は条件の一部。実際に店舗物件の契約や内装工事、キッチン設備などが進んでいて、実際の金銭的投資が必要条件になっている国がほとんどです。つまり、専門学校卒すぐに海外で独立開業することは、
法規・手続き面からも現実的に難しいため
(理論的には可能でも現実的には非常に難しい)
また、投資家ビザの審査官は「経営経験がない若者が成功できるか?」という点を非常に厳しく見るため、ハード面から言っても現実的ではないというのが実情です。
ただし独立開業を見据え、まずは海外の飲食店などに研修やインターンとして就労する「J-1研修・インターンシップビザ」で、現地でトレーニングを積み、様々なことを学ぶところから始めるのが現実的かもしれません。「J-1研修・インターンシップビザ」では、最大18ヶ月の滞在が可能で(※2025年11月現在)、インターンや研修プログラムの内容が異なれば、繰り返し申請が可能という点もメリットになるでしょう。
インターン研修例)
・最初の18ヵ月:調理現場の基本研修
・次の18ヵ月:店舗運営研修
・次の18ヵ月:人材マネージメント研修
3,立地選定と物件の契約
このフェーズは、実際にマーケティングのリサーチのほか、物件探しは日本国内でも同じではありますが、ラーメン屋において立地選定は成功の明暗を分ける最大要素となりますので、事前リサーチが非常に重要だということを認識しておきましょう。
4,保健・衛生・建築・消防関連手続き
アメリカの場合、保健局への飲食店営業許可申請のほか、食品衛生資格者の選任など、保健・衛生に関する手続きが必要となります。なお、店舗でアルコールを出す場合には、酒類取り扱いライセンスが必要となり、州によってその費用もハードルも大きく変わってきます。
消防関連の手続きにおいては、店舗の建築許可が必要となるうえ、キッチン設備の設置は消防規則に準拠する必要があります。その他、消火器、排煙設備、火災報知器などが正しく設置のか、消防局によるチェックもあります。
5,税務・労務・保険関係
日本の法人税と同様、アメリカでも事業者が収めるべく税金はもちろんありますし、人を雇用した場合の労務管理であったり、店舗火災などの事故などに備えた保険加入なども必要となってきたりします。日本同様、これらの業務を行う裏方の人も必要となりますので、調理技術や味だけで勝負するのが難しいと言われる由縁です。
少々長くなってしまいましたが、上記では代表的な手続きや申請について取り上げてみました。調理師専門学校を卒業して、
すぐに海外で出店できる可能性は限りなく低い
のが現実ではありますが、インターンなどが募集されているようなら、ビザ取得の可能性も高まりますので、まずは現地の味の傾向を知ることや、周りの人とのコミュニケーションを取れるようにするためにも、数年は修行をした方が良いかもしれません。
■関連記事
実は持ってた方がいい?!ラーメン職人と調理師免許の深い相関関係

法規性は遥かに厳しいものの出店数は+2〜3%の成長傾向
これらのように専門学校卒業後、ほんの数年でラーメン屋を開業するのは、相当にハードルが高く、もちろん語学力の問題もありますし、何かしらのコネクションや資金的なサポートがないと現実的には難しいというのが実情です。ただし、数に限りはありますが、インターン募集などで採用されれば正式に就労できるビザも取得できるので、
将来的な独立開業を見据えて海外で下積みをする
という土台を整えることは可能です。
ある意味、このプロセスを踏むのが最も一般的で、最も現実的かもしれません。海外出店の難しいところは、特にアメリカにおいては週単位でルールが全く異なる、必要な手続きや必要な資金なども異なります。もちろん、ニューヨークやシカゴ、ロサンゼルスなどの主要都市ほどハードルが高く、逆にテキサス州・フロリダ州などはそのハードルが若干低いようです。
まずは、開業するまでに全力を注がなければなりませんが、言うまでもなく
開業がゴールではなく成功が目標
でありますので、繁盛するためにも様々な仕掛けや広告宣伝が必要となりますし、お客様から支持されるためには、当然味も納得いくものでなければなりません。ラーメン屋の場合、良質な材料を使うほど美味しいものが作りやすい訳ですが、当然原価率が上がって採算性を圧迫します。
この辺は、当校調理高度技術学科・2年制でも「経営学」を学びますし、ましてや独立開業して自身がオーナーを務めるとなると、当然意識しなければならない点であることは言うまでもありません。苦労のすえ、ようやく開店に漕ぎつけた自身のラーメン屋ですから、1年で閉店を余儀なくされるようなことは絶対に避けなければなりません。
なお、日本国内における飲食店において、一般的に言われる平均廃業年数(寿命)は
1年以内で30%・3年以内で約70%が廃業
と言われていますが、アメリカにおいては「初年度倒産率は約17%程度」であることは前回記事でもご紹介いたしました。足元では、ラーメン店は非常に人気が高く、他店も含めて競合性が高いのも実情ですが、
市場の規模や裾野は拡大傾向にあり
日本ならではの豚骨や味噌といったラーメン以外にも、現地の嗜好に合わせた創作系ラーメンなど、様々なラーメンが誕生しつつあります。言うなれば、寿司でいうところの「カルフォルニアロール」は、まさに現地の嗜好向けにアレンジされた巻き寿司であり、それと同じような現象がラーメンにも生まれつつあり、成長余地がまだまだ大きいというのが多くの見解です。
競合が増えれば、当然淘汰も進んでしまうのがビジネス界の常。
いくらラーメン需要が高く推移していたとしても、現地の人に支持されなければ、即閉業に追い込まれてしまうのは日本でも同じ。いくら味に自信があったとしても顧客のニーズをしっかりと把握し、それをサービスに反映することができなければ、
本当の意味で「食」を提供していることにはならない
ので、その辺のりリサーチも含めて、開業前にインターンや研修生として現地のラーメン店に就職することがどんなに重要なことかが、理解できるのではないかと思います。最後になりましたが、上記でお伝えした「J-1研修・インターンシップビザ」は、当然若ければ若いほど審査が通りやすい傾向にあるようなので、
若いうちほどチャンスが多い
ということも、頭に入れて具体的な独立開業までのロードマップを描いておくと良いでしょう。
■関連記事
夢は大きく海外出店!卒業から独立、海外出店までのサクセスストーリー